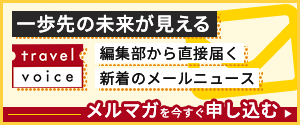人々の手の中に常にインターネットがある世の中になり、旅行・観光業でもオンラインを使った取引やマーケティングが当たり前になった。特にオンライン旅行会社(OTA)をはじめ、オンラインでビジネスを行なう旅行・観光関係の事業者の勢いは際立っているように見える。
しかし、「旅行・観光業のIT活用の現状は、本来できることのうち10%以下」と話すのは、日本オラクルの専務執行役員でクラウド・アプリケーション事業統括の下垣典弘氏だ。旅行・観光業は最も魅力的で、日本の未来を担う産業だと語る。旅行・観光業がIT活用をもっと高めることができたらどんな未来が拓くのか。その実現にはどうすればいいのか。新年にあたり、下垣氏に旅行・観光業界の課題とともに、進むべき道を聞いた。
企業の事業活動の基盤となるデータベース管理システムやソフトウェア開発を行なう同社は、業種的には異業種であるが、旅行・観光業の中枢で、企業活動を支援するパートナーでもある。
ITで変わる旅行・観光業の可能性
下垣氏は日本オラクルにとって、そして自身にとっても、旅行・観光業は「業種・業態が集約された最も面白い事業」と語る。ITだけで完結できず、今後もITが関わる余地が大きいというのが、理由のひとつだ。
OTAの成長は著しいが、すべての旅行者の予約がオンラインだけで完結することはない。例えば、要介護者など特別な配慮が必要な旅行者の場合、人の介在が不可欠だ。Eチケットが浸透した航空券販売でも同様。この状態を、「サービスのプリプロセスの部分はいまだにハイブリッド」と下垣氏は表現する。
同氏が観光業に注視するもうひとつの理由は、旅行・観光分野の消費者へのアプローチで新たな可能性があること。オンラインの世界では多くのサイトやアプリが乱立する一方で、消費者の行動は固定化し、商品や目的によって実際に利用するサイトやアプリが数か所に限定されるようになっている。
しかし、旅行の場合は消費者が旅行を決めてから目的を達成するまでの前段の部分、つまり、旅行業界が注目しているタビマエ・タビナカ・タビアトの旅行プロセスの最も初期の段階で、「目的(旅行)を想起させる様々なルートが、世の中で最も千差万別でありながら最もデジタルコンテンツがされていない」と、下垣氏はIT活用の可能性に期待を示す。
これらを踏まえると、「旅行は業界内に留まらず、新顧客を作って数多くリピートしてもらい、新しい地域に出てもらう、または日本に来てもらうという点で、異業種から見るとすごく面白い産業」だと下垣氏。ITの活用でまだまだできることは多く、下垣氏は「これから日本を元気にできるかどうかの最も重要なポイントでもある」と、旅行が果たす役割に期待を示す。
下垣氏はこうも語る。「2020年(東京五輪開催)が終わった後、日本に行きたいと思う人をどれくらい増やせるか」――。これは旅行者だけではない。「人口減の日本が経済国として生き残る道を考えたときに、労働目的だけではなく、住みたい国として惹きつけられるか」。それほど魅力的な国になれるかどうかにも関与するという。「旅行・観光業がこの先できることは大きい」と、未来を拓く可能性にも言及する。
歴史を捨てる勇気が未来につながる
しかし、「一方で旅行・観光業界は古い」と下垣氏は続ける。いまだに何度もキャンペーンを打つことを考えるのは、業界の内側しか見ていないから。「ITの導入というより、発想が遅れている」と、指摘する。
無形商品である旅行はオンラインとの親和性が高いと言われているが、下垣氏は旅行・観光業のITの活用の現状を、「本来できることのうち、10%以下だと思う」とかなり低い見方を示す。
日本企業全体ではどうか?
同氏は「(IT活用の現状を)製造業は30%、金融業は35%」とみており、他産業に比べても低い数値だ。しかし下垣氏は「国内だけで見れば50歩100歩。海外と比べると大きな差がある」と、日本企業全体が海外のトレンドから遅れて、構造的な問題があることを指摘する。
 下垣氏は、この要因はインターネット黎明期の日本企業の対応にあるとみている。企業がホームページを作り出した1990年代、欧米の企業は重要分野と捉えて投資をし、内製していた。これに対し、日本企業は「とりあえず予算の中で作る」程度の判断で、外注で済ませた。だから企業側は目利きができず、構造的に考えられていない状態になったという。
下垣氏は、この要因はインターネット黎明期の日本企業の対応にあるとみている。企業がホームページを作り出した1990年代、欧米の企業は重要分野と捉えて投資をし、内製していた。これに対し、日本企業は「とりあえず予算の中で作る」程度の判断で、外注で済ませた。だから企業側は目利きができず、構造的に考えられていない状態になったという。また、広告配信でも6兆円産業と言われるうち、デジタル広告は1.5兆円と4分の1程度で、海外と比べて小さい。しかも広告会社に丸投げで、「本当に適した形で行なわれているかも疑問」と下垣氏。消費者の行動に応じて適したメディアを提供しようという、DMP(データマネジメントプラットフォーム)的な考え方ができていない企業が多いと話す。
こうした状態を打開するために下垣氏が提案するのは、「日本のIT業界が30年かけて作ってきた構造自体を、自己否定しながらでも変えていくこと」。下垣氏もその年月、身を置いてきた業界であるが、それでも「歴史をどこまで捨てられるかの気持ちが大切」だと呼びかける。
今、下垣氏が力を入れているのは、60代以上の経営者に対する世の中の変化とITの説明だ。若いスタッフが時代を見て取り組もうとしていることを、経営陣が理解し、スムーズに導入できるようにするためだ。今は「ITを知らなければ経営できない」と言われているのに、「その件は担当者に任せてるから」と答える経営者もいるが、いざというときにバリアになっているという。
旅行・観光業でも、同じことが言えるだろう。
変化への大きなチャレンジ
では、どうすればITの真の有効活用ができるのか。旅行の場合、まず、前述した旅行プロセスの前段である「旅行を想起させるきっかけ」部分に大きな可能性がある。
「その旅行業界の前の部分にどうやってエンゲージ(結びつきをつくる)するか。それをどう知るかがポイントになる」と下垣氏。今の若者は、企業のホームページなど、誰かが作ったサイトはどこかに恣意があると思う傾向があるという。そのため、自分が非公開で繋がるインスタグラムなど、SNSやメッセージングサービスをより信頼の置ける情報として利用。日々忙しく、時間が限られるなかでも「自分が書き込むところにエンゲージする」という。
また、広告の部分でも「使っている広告費を、どうビジネスに繋げていくか」の観点で改善の余地があるという。ここで下垣氏は、ソーシャルエンゲージを強化したサッポロビールの事例を紹介。業界4位の同社の場合、大規模なマーケティングブランディングは収益効率が悪かったことから、SNSでのファンとの直接的な関わりを増やしてきた。その結果、公式Facebookの「いいね!」は導入時の約2倍(21.9万人)となり、ウェブサイトの流入数が135%に向上。平均エンゲージメント率は競合他社の3倍になった。
下垣氏は、「仮にファンの数が8000人になったとして、その向こうに100人の友達がいれば80万人に届く。80万人にリーチする15秒のスポットCMを取れているのはどれくらいあるのか」と、ソーシャルエンゲージの効果を強調する。
また下垣氏は、従来からITに取り組んでいた企業にとっては、「導入時の過去の払拭も重要」と語る。旅行業界は早くからオンライン活用を行なっていたが、もし、過去の取り組みが気に入られていないのであれば、見向きもされなくなっている。だから「変わったことを認知させ、もう一度試してもらう」ことが必要なのだという。もちろん、このほかにもまだ活用しきれていない様々な可能性があるという。
進む意識変化
下垣氏が担当するクラウド・アプリケーション事業は現在、2日に1社の新規顧客が入り、旅行・観光分野では特に地方自治体の利用が増えているという。しかも最近は横並びの日本のなかではなく、海外に目を向けた質問が増えているなど、変化の兆しを感じているという。
「旅行・観光業界の本当のチャレンジは業界改革。ここでITが関与する」と下垣氏。これが実現しなければ、「オンラインの波に乗って進出する海外企業にのまれてしまう」と、日本の将来を危惧する。
旅行・観光業界は自らの収益向上とともに日本の未来を拓く力を持っている。そのカギを握るのはIT活用。真に活用するために旅行業界が越えるべき山は大きいが、下垣氏は「日本の力を変えるためにこの2年が勝負」と力を込める。そのゴールには、人々の活力ある未来が広がっているはずだ。
聞き手:トラベルボイス編集部 山岡薫
記事:山田紀子(旅行ジャーナリスト)


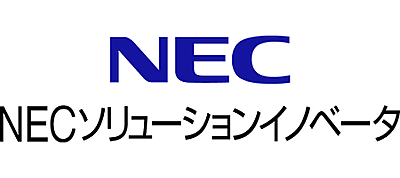















 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】