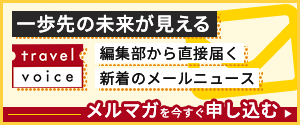こんにちは。観光政策研究者の山田雄一です。
先日、EUから新しい観光指針が示されました。
参考:欧州委員会、各国に「観光目標」の転換を勧告、旅行者数や泊数からの脱却し、社会・環境・経済的影響のデータ重視を【外電】
ここで示された指針では、観光を取り巻く環境が、社会経済環境変化の潮流の中で、どのように変化していくのか、その変化に対していくには何が必要なのか、ということが示されています。
詳細は、原文を参照いただければと思いますが、彼らはデジタルと環境対策が絡み合いながら、新しい社会経済を形成していくであろうと展望しています。興味深いのは、その変化に対応していく手段として、中小企業の強化を掲げていること。ホスピタリティ産業は、米国資本の独壇場となりつつありますが、欧州としての対抗策として示された今回の指針については、「なるほど~」という印象を受けました。
もともと欧州は、都市部を含め、大規模な開発は抑制されており、地方部(リゾート)では、外部資本の参入自体ができないことが多いといえます。これが米国資本に対する一種の参入障壁となり、域内事業者の保護につながっていいます。しかし、観光が競争である以上、事業者が提供するサービスが一定の水準に達しなければ、結局、顧客は離反してしまいます。地域として、観光領域の競争力(誘客力)を獲得しつつ、域内の事業者を活かしていくためには、中小事業者自身が、その経営力、競争力を高めていくことが必要となるのです。
とはいえ、資本も人材も限定されているのが中小事業者であるわけで、資本も人材も、また、経営系の知財も備えたグローバル資本と真っ向勝負ができるはずがありません。
本レポートでは、その方策として、デジタル対応の強化、ベスト・プラクティスの提示、人材育成…といったことを掲げています。これだけなら日本のソレと大きく変わらないのですが、欧州が面白いのは、これらに加え「観光振興のルール、フレームを変えちゃおう」というところ。
具体的には、観光振興に関わる指標を経済面だけでなく、環境、社会へ広げ、かつ、それを包括する観光統計フレームを構築。さらに、それに連動するように、中小企業に欧州のエコ認証であるEMAS(Eco-Management and Audit Scheme:EUの環境管理制度)への登録を促し、商品についても環境フットプリント(欧州委員会による環境パフォーマンス測定の手法。製品に関するPEF=Product Environmental Footprintと、組織に関するOEF=Organisation Environmental Footprint がある)導入を促します。そして、これらの動きに対応する中小企業支援に特化した資金調達手法を用意する流れです。
こういったフレームを作ることで、デジタル対応強化、ベスト・プラクティス提示、人材育成促進といった取り組みが、一つの流れとなって強力な意味を持つことになります。なぜならこれらは、欧州が支援することになる新しい環境対策経営に必要な手段だからです。
もちろん、欧州のこの方針に従わなくても、観光事業をおこなうことは可能です。しかし、域内の中小事業者に対する「えこひいき」な制度と支援制度を作ることで、競争力の底上げを図ることができる、という仕組みです。
もともと、観光による地域振興において重要なことは、地域に観光客が来ることではなく、観光客の消費活動が地域の付加価値形成につながることです。しかし、観光客来訪~観光消費発生~付加価値創造(域内分)~波及効果の関係は必ずしも直線的ではないことは、過去の分析でも明らかになっています。
一般的に言って、観光客来訪 ―観光消費発生のリンクは、ブランド力のある(グローバルな)ホテルチェーンが強く、付加価値創造(域内分)― 波及効果のリンクは、地元密着の中小事業者の方が高くなります。
ブランド力のある事業者が参入すれば、観光客数も観光消費も増大しますが、増大したほどの付加価値(域内分)は創造されず、波及効果も限定的です。他方、地元の中小事業者だけの取り組みでは、需要者となる顧客の嗜好に応えることが難しく、地域間競争に劣後しやすくなります。
欧州では、そもそもの観光目標を変えてしまい、「もう量的拡大は求めないので、環境や社会に貢献する中小企業を”えこひいき”します」という指針を出すことで、この矛盾を解消しようとしているわけです。つまり、この欧州勧告の内実は、環境という「錦の御旗」を利用した地域振興策であり、保護主義的な中小企業振興策なのです。
自動車業界では、急速な電動シフトについて「欧州の自動車メーカーが、トヨタのハイブリッドに対抗できないため」と囁かれることが多いようですが、本勧告も、それに近い思惑が垣間見えます。
ただ、自動車の電動シフトがそうであるように、温暖化対策は人類にとっての課題であり、正義でもあります。既に「飛び恥」という言葉が生まれてきているように、観光分野においても、カーボン対策は、顧客の「ニーズ」としても定着していくことになるはず。
その「ニーズ」に対応できなければ、地域がどう考えようと、いずれ、顧客の支持を失い、競争力を失うことになります。であれば、事前に新しいフレームを設定し、域内事業者が早期にミートし、競争力を高めていけるように支援する方が得策といえます。
おそらく、域内の中小事業者の対応が進んでくれば、それを武器としたマーケティング/ブランディングを欧州は展開していくことになるでしょう。それによって、欧州のデスティネーションとしての競争力は高まり、また、顧客は「あえて」中小事業者を選好するになるはず。なぜなら、時代に合った彼らの行動、提供サービスそのものが、来訪動機となっていると考えられるからです。
電動化を先行して取り組んだ欧州自動車メーカーが、2030年には世界をリードするだろう…という思惑と同様だと考えれば理解しやすいのではないでしょうか。なんとも、「戦略とはこうあるべき」という見本のような勧告なのです。
もっとも、欧州の中小事業者が、サービス業に適合した経営力(資金、人材、知財)を持ち、なおかつ、デジタルの活用と環境対策という新規要件に対応していくことができるのかという点は未知数ですが――。
供給量問題
ここで改めて、「観光客数(泊数、消費額を含む)」について考えてみましょう。
観光客数が増えれば、のべ泊数、消費額も積み上がっていきます。総消費額に一定の係数をかけたものが付加価値額となるから、観光客が増えれば、地域経済は潤う…というのがマクロ的な構造です。
ただ、実際の社会では、若干異なります。
観光客が増えると、供給量(例:ベッド数、観光バス)も増大します。供給量を増大させた事業者は、自身の経営のために、より多くの観光客を集めようとすします。順調に客数が増えれば、オーバーツーリズム状態となっていくし、逆に増えなければ供給過剰による過当競争となり、ブランド力の弱い地元/中小/昔からある施設を中心に、価格が下落していきます。
これは、人数面でのインパクトが小さいラグジュアリー市場でも同様です。
ラグジュアリー・ブランドが入ってくれば、宿泊単価は大きく跳ね上がるため、オーバーツーリズムにつながるような人数面は抑制しつつ、観光計画の目標値である消費額達成に貢献することになります。そのため、地域も、こうしたブランドが入ってくることを喜ぶ傾向がみられます。
ただし、いくら消費単価が上がったとしても、そこで生まれる付加価値が地元に落ちなければ、地元経済への貢献はありません。その地域で消費が発生することと、経済効果(付加価値)が地域に広がることは、必ずしもシンクロしないということを意識しておく必要があります。
地域にとって必要なことは、消費額(売上額)、付加価値の総量ではなく、そこから生み出される良質な雇用や、調達(B2B)です。その考え方に好適なのは、供給量を制御した上で、供給量に沿った需要(ちょっと上回る)を着実に獲得することにあります。そうすれば、自然と、域内事業者が提供するサービスの価値が上がり、生産性の向上にもつながることになるからです。
ただ、供給量制限がかかると域内での競争環境が緩和されるため、経営努力をおこなわない事業者が出てきて、中長期的に地域全体のブランドを毀損することになってしまいます。その状況を避けるためには、域内事業者の経営水準を高めていく取り組みも並行しておこなっていく必要があります。
欧州は、これを目指す戦略フレームを明示したことになります。
日本の場合
では、日本ではどうでしょうか。
日本は、基本的に投資は自由であり、不動産所有についても制限はありません。都市計画法に基づく用途地域はあるものの、法的な制限は乏しいと言えます。また、温泉地やリゾート地では、そもそも都市計画地域に該当していなかったり、都市計画地域でも用途地域が定められていないことも多いようです。農地取得(転用)や、保安林、自然公園指定されている山林については、一定のハードルはありますが、実態は、むしろ空洞化が進んでいる状態ですから、あえて、そうした未開発地域へ乗り出す必要性は低いでしょう。
つまり日本では、事業者によって、事実上、ハードルは無いといえます。
これは、米国の状態に近いのですが、日米で大きく違うのは「日本のホスピタリティ産業の競争力が低い」という部分。日本企業のブランドと、米国系チェーンのブランドでは、その差は圧倒的となっているのが現実です。
なぜ、米国系チェーンが競争力を持ち得たのかと言えば、米国内に厳しい競争があったから、と言えるでしょう。1990年代の後半以降、米国内のホスピタリティ産業は、財務、マーケティング、レベニュー、顧客管理などなどの経営技術を高め、激しい「つばぜり合い」を展開。その競争を勝ち抜いた事業者が「海外に打って出る」権利を獲得しました。
強力な経営力を持ったチェーンが参入してくると、日本、特に地方の事業者は、太刀打ちができず撤退、衰退することになってしまいます。
米国でも同様のことが起きていたはずですが、回り回って米国内資本ですし、その活動が、産業全体の生産性向上につながっていくことで大きなメリットもあります。観光消費の場所だけを提供する日本とは、構造が異なっているのです。
顧客の視点は、また異なる
他方、利用客となる顧客の立場から言えば、日本の観光地に外資が参入することは悪いことではありません。ブランディングが徹底されている事業者であれば、期待値に対する下振れリスクは低いし、より洗練された、合理的なサービスを享受できると期待できるでしょう。
そもそも、外資ブランドに「人が流れる」のは、顧客が、そういう選好をおこなうからであって、外資が無理やり客を奪っていくわけではないのです。
個人的な経験で言っても、「ココに泊まるのは罰ゲームだろう」と感じる宿泊施設があるのも事実です。率直なところ、21世紀に入ってから、それなりの規模のリノベーション投資をおこなっていない施設は、かなり厳しい状態にあると言えるのではないでしょうか。
私個人は、業界関係者として、投資ができない理由は理解できますが、顧客はそれに配慮する義理はないことも、十分理解できます。
地域産業政策のアメとムチ
忖度しない顧客の支持を取り付けることは、観光において、当然のことであるし、大前提です。ただ、それを漫然と受け入れ、自由競争に任せれば、地場の観光・ホスピタリティ産業の基盤を失い、観光による地域振興は展開し得なくなります。
この構図は、商店街とショッピングセンターの対比に近い状態です。利便性の点で、ショッピングセンターは圧倒的。人々は、商店街を潰すつもりは無く、便利だから、快適だからショッピングセンターを利用していたわけですが、結果、商店街は衰退し、中心市街地は空洞化していきます。
とはいえ、大店法が機能していた時から、中心市街地の空洞化は進展していました。この背景にはモータリゼーションとか、地方部の人口減少などがあったわけですが、一点、言えることは「保護」をしても、競争力は高まらなかったということ。
1990年代初頭、私は建設会社の職員として、都市再開発の現場調整に関わっていましたが、そこで感じたのは、自身の内部環境ではなく、外部環境に原因を求める「他責」的な商店主の多さでした。既に、利便性において商店街とショッピングセンターでは、圧倒的な差ができていたにも関わらず、です。
この前例を考えれば、外資ブランドの進出を止めるだけでは、解決にはならず、むしろ、消費者(顧客)の選択を歪めることになるでしょう。
重要なことは、「一定の保護政策を展開しつつ、一方で、新しい環境への対応をおこなわない事業者は支援対象から外していく」というアメとムチ対応となっていくと考えることができます。
観光政策の方向
観光政策をどのように考えるのか、という議論には多くの変数があり、一概に整理はできません。
しかし、欧州が「環境への対応を通じて、いかに地場事業者の競争力を高めるのか」ということを明確にしてきたことの意味は大きいでしょう。
これを、単に「これからはオーバーツーリズムに反省に基づくサスティナブル・ツーリズムだ!」と捉えるのではなく、観光による地域振興とはどういうことなのかということを見つめ直す必要があります。
コロナ禍の混乱が続いているなか、地方部でのホスピタリティ産業をどのように捉え、どのように対応していくのかということを考えていくことは、非常に重要なテーマではないでしょうか。
参考記事:
【編集部・注】この解説コラム記事は、執筆者との提携のもと、当編集部で一部編集して掲載しました。本記事の初出は、下記ウェブサイトです。なお、本稿は筆者個人の意見として執筆したもので、所属組織としての発表ではありません。
出典:DISCUSSION OF DESTINATION BRANDING. 「重要なのは「地場の中小事業者」
原著掲載日: 2022年2月13日



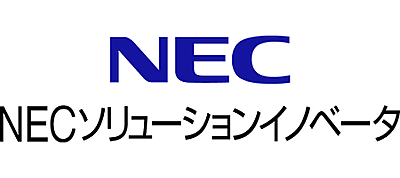















 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】