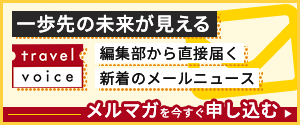こんにちは。観光政策研究者の山田雄一です。
日本版DMOが政策として展開されるようになって以来、観光推進組織の創設や法人化が進んでいます。かつて、日本の観光協会の多くは任意団体でしたが、着地型旅行の概念が登場し始めた2000年台の中頃から、各種の契約行為や主催旅行の催行などを目的に、法人格を取得する動きが顕在化してきました。
今回のコラムでは、こういった経緯を分析しながら、DMOにとって妥当な「法人格」とは何なのかを考察してみたいと思います。
法人化が進んだ2000年代
例えば、2001年には株式会社南信州開発公社が、2003年には株式会社ニセコ観光協会が創設され、2004年にはNPO法人ハットウ・オンパク、翌年の2005年には同じくNPO法人阿寒観光協会まちづくり推進機構、一般社団法人白馬村観光局が創設されています。
2005年の第3種旅行業の特例は、こうした動きを更に加速させることとなり、株式会社昼神温泉エリアサポート(2006年)、松之山温泉合同会社まんま(2008年)、株式会社小値賀観光まちづくり公社(2009年)、一般社団法人飯山観光局(2010年)などが続々と創設されるに至りました。
多様性があった法人格
観光庁は2010年、当時、全国で特徴的な動きをしている観光推進組織を「地域いきいき観光まちづくり2010年」として取りまとめています。現在のDMO議論以前の状況ですが、このリストを見て気がつくところがあるのではないでしょうか。そう。法人格がかなりバラついているのです。
特に、2000年代に生まれた「駆的な組織」は、株式会社やNPOを採用することが少なくありません。しかし現在では、ほぼ「一般社団法人」の一択となっています。
理由として、社団法人が一般と公益に区分されたことで、公益性を排除した一般社団法人を簡単に創設可能となったということが、大きく影響していると思われます。
さらに言えば、観光協会のトップである日本観光振興協会の法人格が、(公益)社団法人であることも影響しているのかもしれません。
ただ、DMOの法人格として、一般社団法人が適切かどうかという点では、疑問が残ります。
そもそも社団法人とは、組合形態を法人化したものです。社団法人では会員を「社員」と呼びますが、社員が共同で対応が求められる課題に対応していくための組織が社団法人となります。これは、私の定義する「クラブ・ソリューション」に当たります。つまり、当事者自身で、または専門家に依頼して問題解決をおこなうのではなく、共通する利害関係者が連携することで解決する手法をとっています。
確かに、DMO概念登場以前の観光協会は、共同事業体、同業者組合、互助会組織という側面が強いものでした。例えば、地域で集客を目的としたイベントを開催したり、行政に何かしらの陳情をしたりする場合、旅館がバラバラでは対応が困難です。一方で、地域の旅館が会員となった組織があれば、対応が容易となります。その意味で、(一般)社団法人という法人格は適切なものでした。
観光協会とDMOの違い
しかしながら、地域のマーケティング/マネジメントを担う今日のDMOではどうでしょうか。観光協会(Tourism Organization)とDMOの違いは、端的に言えば、観光協会では行動原理が事業者視点であるのに対し、DMOは顧客視点であるということです。
事業者視点では、不利益を生じる事業者がいる取り組みを進めることができません。つまり、「誰も反対しない」取り組みしかできないことになります。それに対して顧客視点の場合、ターゲットとする顧客に「刺さる」かどうかが判断基準となります。その結果、一部事業者から反対意見が出されることがあっても、地域としての競争力を高めることが優先されるのです。
例えば、地域の宿泊施設や飲食店を紹介する際、事業者視点では、会員全てを紹介することになるし、その紹介コメントも当たり障りのないものとなりがちです。対して、顧客視点であれば、ターゲットに適合する事業者を優先的に取り上げ、その紹介コメントも、ターゲットに響くようなものを選ぶことが可能です。
そうやってメッセージを鋭いものにしなければ、数多ある観光地の中で、埋没してしまうからです。特に、チャレンジャー/ニッチャー戦略を展開すべき地域において、これは重要なことです。
ただ、現実的には、ターゲットを設定した時点で「誰も反対しない」ものとなりがちです。また、仮に特定セグメントをターゲットとしても、それ以外の市場についても、ジェネラルな対応をするという判断に至ることが多々あります。そのため、投入できるリソース(資金や人材、時間)が分散し、集客のしきい値を超えることができない、という顛末を迎えてしまうのです。
マーケティングの重要性が叫ばれ、以前に比べて多くのマーケティングデータが取得できるようになったにもかかわらず、結果として、やっていることはあまり変わらない…というのが実情なのです。
意思決定プロセスの問題
なぜ、「DMO」を標榜しながら、そうなってしまうのかという点については、各所で指摘されていますが、筆者は「一般社団法人」という形態に一因があると思っています。
前述のとおり、一般社団法人とはもともと、互助会組織を運営するのに適した法人形態でした。なぜなら、社員(会員)を集め、社員から会費を集め、その資金の使途については、社員から互選された理事が決定するという形態だからです。
さらに、一般社団法人では、いわゆる会員要件を設定することで、参加者を選別することも可能です。正会員と準会員などに分け、理事は正会員から互選するといったことが可能となります。
また、議決権は会費口数に比例することが多のですが、地域の特性上、大手事業者だからといって議決権確保のために、あからさまに口数を増やすということが難しくなります。そうなると、議決権は事業所としての数が多い中小事業者が握ることになってしまいます。
こうした状況では、構造的にマイノリティの意見は通りにくく、新しいことをしたいという若手経営者や外部からの参入者はその組織(一般社団法人)に参加しない――という事態も招いてしまいがちです。
そのため、外部から専門人材を招聘したとしても、その専門人材は、顧客視点での戦略立案は難しく、まずは、社員(会員)の意見を聞くところから始めなければならないことになります。
パレートの法則で言えば、地域の観光は2割の事業者が牽引しているにもかかわらず、残りの8割の事業者の声を踏まえないと事業を組み立てられない構造にあることになります。その結果、DMOと名前を変えても、結局「これまでと同じ」路線が強化されやすくなるわけです。
一般財団法人を選択肢に
こうした意思決定プロセスの構造的な問題に対応するには、私は、法人格を一般財団法人とすることが有効ではないかと考えています。
一般社団法人も、一般財団法人も、外形的には大きな違いはないのですが、社団法人は社員という人の集まりが基軸になっているのに対し、財団法人は基金という資金が基軸となっています。そのため、財団法人には議決権を持った会員という概念が存在しません。賛助会員制度を設けている法人は多数ありますが、これは、会費を納めるだけであり、議決権はなく明示的なリターンも不要となります(会員特典を設けている法人はありますが)。
一般財団法人の執行部(理事、監事)は、社員総会にて選出され、その事業計画、決算も同様です。一方の一般財団法人の場合は、第3者機関的な評議員会にて選出、了承されます。
さらに、一般社団法人は年会費が基礎的な収入であるため、事業計画も単年度でつくりあげていくことが求められるのに対し、一般財団法人の場合、基金をもつことで中長期的な時間軸での事業計画を立案することが可能です。
特に、現在、各地で検討が始まりつつある宿泊税が顕在化してくると、行政は持続的にDMOに対して活動資金を拠出できるようになります。一般財団法人であれば、その活動資金を単年度の事業費としてだけでなく、数年間にわたって自立的に利用できる基金として受領することもできるでしょう。
基金は株式会社の資本金に近い性質を持ちますが、財団法人の場合、基金に寄付した時点で、その寄付者は資金に対する一切の権限が喪失します。つまり、寄付をしたからといって、議決権が高まるわけではないし、配当金などが得られるわけでもないのです。(寄付者が自ら財団法人を創設し、その評議員になることで、実効的に支配するということはあり得る)。
こうした違いによって、一般財団法人の執行部は、会員(事業者)ではなく、法人に設定されたミッションに従った行動を行いやすくなります。専門人材を招聘し、ある程度痛みの伴う取り組みもおこないながら地域の競争力を高めていくには、より好適な法人形態だと言えるのではないでしょうか。
結局は運営の問題
もっとも、一般財団法人であれば、全て解決ということにはなりません。評議員会のみが「お目付け役」になる構造は、執行部の緊張感を薄める理由になるかもしれませんし、実際の行動においては各事業者とのパートナーシップが必要になります。もしも基金額が少なく、(宿泊税などを原資とした)行政からの支援も少なければ、結局は会費に頼ることになってしまいます。
一方で、一般社団法人であっても、社員(事業者)が、観光協会とDMOとの違いを認識し、DMO活動を支えるような体制が取れるのであれば、実行上の問題はとくにありません。一般財団法人よりも、会員との距離が短い分、むしろ、より強力な体制となることも期待できるメリットもあるでしょう。実際、海外のDMOでは、一般社団法人と同様の形態となっている組織が多数確認できています。
その意味で、結局は、運営の問題ということになるでしょう。
しかし、人間というものは、自身が経験していないことを理解することは難しく、まだ活動してもいない段階で意識を変え、合意をとるというのは至難の業です。
DMO活動を進めていくのであれば、進めやすい法人形態をあらかじめ選択し、そこで実績を提示していくというアプローチについても検討すべきではないでしょうか。特に、宿泊税など、持続的な観光振興財源を得る地域においては、それを機会に法人形態についても再考していくことが必要だと言えます。
※編集部注:この解説コラム記事は、執筆者との提携のもと、当編集部で一部編集して掲載しました。本記事の初出は、下記ウェブサイトです。なお、本稿は筆者個人の意見として執筆したもので、所属組織としての発表ではありません。



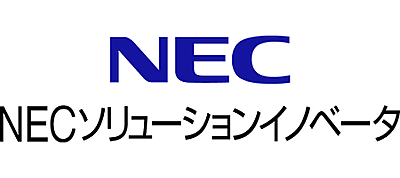















 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】