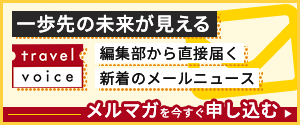バス事業など人の移動にかかわる事業を展開するWILLER(ウィラー)が2021年3月、「MaaS Meeting 2021」を実施した。スマートモビリティ・チャレンジ・シンポジウムでは、交通と都市政策の連携について議論。MaaSは、地域の交通インフラの整備という側面と同時に、旅行者の地域内での周遊を促す観光インフラとしての側面があるが、交通事業者だけでは成り立たず、行政、IT事業者などさまざまなステークホルダーが関わるプロジェクトになる。シンポジウムでは、それぞれの視点からMaaSの今と未来が語られた。
大阪府、MaaSはまちづくり
行政の視点として、大阪府スマートシティ戦略部総括主査の服部健太氏が登壇し、大阪府がスマートシティ戦略のもと進めているスマートモビリティについて説明。現在、池田市伏尾台で地域課題の解決に向けて産官学の協業で取り組んでいるMaaSの構築を紹介した。
そのなかで、服部氏は、ラストワンマイルの問題解消に向けたAIオンデマンド交通の普及について、運行主体、マネタイズ、既存交通事業者との共存の3つの課題を指摘。このうち、マネタイズについては「エリアと事業をそれぞれ単独で考えたのでは収益化はできない」との考えを示した。
エリアについては、ユーザーである住民にとって市町村の境界は意味がないことから、単独の市町村での事業モデルでは利益を出すのは難しく、中山間地単独で費用対効果を考えては事業モデルは成立しないとした。
事業については、運賃収入だけでは必ず赤字になるため、さまざまなサービスをMaaSとして結びつけ、持続可能な事業モデルを構築していく必要性を強調した。
服部氏は、それぞれの単独をつなげるためにはデータの有効活用が必須とし、事業を回していく中で蓄積されたデータを分析し、まちづくりや交通政策に効果的に活かしていく方向性を提示。行政の視点から「MaaSは、まちづくりにつながる」とまとめた。
京阪、MaaSで訪問者の行動変容を
事業者の視点からは、京阪ホールディングス執行役員経営統括室経営戦略担当の吉村洋一氏が、京都氏洛北エリアで進めた「奥京都MaaS」実証事業で、課題となっていった観光客の分散化に取り組んだ事例が紹介された。
MaaSシステムの開発・運用ではJR東日本と協業。バスだけでなくグループ会社の叡山電車、大原エリアではドコモ・バイクシェアも組み込んだ。
奥京都MaaSアプリでは、個人でも洛北の各スポットを周遊できるように「旅の行程管理機能」でモデルコースを提案。公共交通機関の利用管理のカスマイズを可能にした。
また、デジタル企画乗車券として、従来の1日券という発想ではなく、利用時間から計算する「24・36時間券」を発行した。これにより、朝観光や夜観光が増え、時間の分散化につながったという。
さらにデジタル飲食チケットも発行し、地域の消費を増やす機会を創出するとともに、デジタルスタンプラリーを企画し、周遊を促した。
吉村氏はこの実証事業を「行動変容を目的とするMaaS」と説明し、「デジタルの力を借りて、顧客体験価値を高めることが大切」と強調した。
 (左から)モデレーターを務めた計画研究所理事兼企画戦略部長の牧村和彦氏、大阪府の服部健太氏、京阪の吉村洋一氏、TOUCH GROUPの原田静織氏単発収支ではなく、クロスセクター効果の視点で
(左から)モデレーターを務めた計画研究所理事兼企画戦略部長の牧村和彦氏、大阪府の服部健太氏、京阪の吉村洋一氏、TOUCH GROUPの原田静織氏単発収支ではなく、クロスセクター効果の視点で
大阪府と京阪の説明を受けて、TOUCH GROUP代表取締役の原田静織氏が、「アプリはダウンロードしてもらって、使ってもらわないと意味がない。アプリでMaaSがビジネスとして成り立つのか」と問題提起。それに対して、大阪府の服部氏は、「ICTにこだわりすぎるのもよくない。利用者のニーズに合わせて、デジタルと、たとえば電話などハイブリットで対応していくも大切。単発の収支だけでなく、クロスセクター効果で将来を見据えながら収益を考えるべき」と答えた。また、京阪の吉村氏は「MaaSの売上と、エリアでのリアルの売上を別々に考えるべきではない」と指摘した。
将来への取り組みについて、京阪の吉村氏は「ニューノーマルによる行動変容に将来的な人口減少によって、定期券収入が縮小する懸念があるなか、経営の仕方、サービスの提供の仕方も変わってくる。MaaSがその手段のひとつになるのではないか」との考えを示し、大阪府の服部氏は「行政だけでニューノーマルを考えてはダメだろう。産官学の枠組みをうまく利用して、標準モデルをつくり、それを横展開してコストを抑えていくことが必要になる」とした。
原田氏は「この先のことは誰も分からないなかで、最初から完璧を目指すのではなく、きちんとエンドユーザーの反応を見ながら、改善していくこと必要」と提言した。
トラベルジャーナリスト 山田友樹


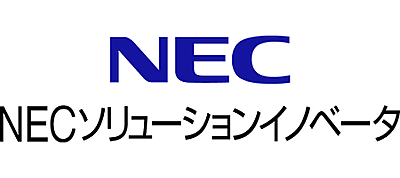















 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】