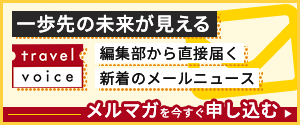日本各地で宿泊施設の再生を手掛けてきた星野リゾート。各施設が地域を訪れる目的となるべく、滞在体験を磨き上げてきた。各地域の事情に向きあいながら、客足が遠のいた施設に宿泊客を呼び込むために、どんな仕掛けをしてきたのか? 星野リゾート代表の星野佳路氏に、その取り組みと、宿泊を軸に地域への滞在体験の向上させる新たな構想を聞いてきた。
人に来てもらう価値を作る仕組み
いま、日本の観光産業は観光による収益性を高めようと、量より質を重視した観光コンテンツの高付加価値化に注力している。しかし、「高」という文字の印象で「高付加価値」を、単純に「高額商品」や「高級商品」と捉えたり、富裕層マーケティングに取り組んだりする動きもある。星野氏は「高付加価値化を考えるとき、単価ありきで考えるとおかしな方向に行ってしまう」と警鐘を鳴らす。
そもそも星野リゾートでは「高付加価値化という言葉で取り組んでいたわけではない」と、星野氏はいう。「当社は、かつては再生案件を手がけることが多かった。人が来ず、破綻した施設に、人に来てもらうための価値をどう作るか」がベースにあり、そこを追求した結果、単価が上がった。
例えば、青森県の文化をテーマパーク的に楽しめる価値を付けたリゾート「青森屋」では、再生当初の客単価は1人平均で約4600円だったが、ソフトとハードの魅力を充実させ、今では2万1000円~だ。星野氏は「需要が増えれば、自然と単価は上昇する。しかし、投資効率目線で取り組むと単価ありきで走ってしまうから、提供している商品の内容が(消費者の感覚と)ずれる」と話す。
では、どのように人を呼び込める付加価値を作っていったのか。星野リゾートでは、各施設の商品開発は現地をよく知る各施設のスタッフが担当し、マーケティングや広報部署のメンバーが参加する会議で商品化を決定する。星野リゾートが重視するのは、商品化した後の顧客満足度だ。毎日、顧客満足度調査を実施し、集客状況や価格、収益などとのバランスを見る。
施設のスタッフは、他施設のデータを確認することも可能だ。星野氏が指示するのではなく「施設のスタッフが取り組みの妥当性を把握し、適切な判断ができる環境を仕組みとして整えることが大切」という。そうすれば、うまくいかない場合は、すぐに各施設のスタッフが自ら修正することができ、他の部署のメンバーとも同じデータをもとに話をすることができるからだ。
そのため、会議で星野氏が反対した企画も、商品化されることもある。星野氏の予想に反して顧客の満足度が高く、ヒットする商品も珍しくない。例えば、「奥入瀬渓流ホテル」が2013年に始めた「苔」コンテンツ。軽井沢で生まれ育った星野氏にとって「苔は珍しいものではなく、魅力になるとは思えず、投資することは考えられなかった」というが、開始から10年を迎える現在も同ホテルのメインコンテンツであり続けている。
「苔コンテンツがなければ、奥入瀬渓流ホテルの再生はなかった。当時、奥入瀬渓流のピークといえば、秋の紅葉だけ。そこに春と夏にも価値を付け、紅葉期以外にも需要を高めることができた」(星野氏)。その後、同ホテルでは需要がなく休館していた冬期に、渓流の「氷瀑」ライトアップなどで「冬の絶景」という価値を作り、通年営業を実現している。
 星野リゾート代表の星野佳路氏
星野リゾート代表の星野佳路氏
地域に連泊して楽しめるシステムを
星野氏が、地域が稼ぐ根本的な方法と考えるのが、タビナカでの消費を増やすこと。宿泊施設への連泊を増やし、滞在時間を延ばすことで、地域に直接お金が落ちる時間を生み出すことだ。
しかし、現在は国内宿泊旅行の消費額の半分を交通費が占めている。これについて星野氏は「飛行機や新幹線など交通事業者や、旅をアレンジする旅行会社が観光から利益を得ても、地域に還元されるわけではない。日本の観光消費額から地域に落ちる金額を増やすには、連泊しかない。日本は諸外国に比べて圧倒的に1回の旅行あたりの宿泊日数が少ない」と、連泊の必要性を強調する。
同時に星野氏は「連泊しにくい理由には、私たちの方にも問題があるのではないか」と、宿泊事業者としての課題感にも触れた。その最たるものは、食事の提供スタイルだ。温泉旅館の宿泊は1泊2食付が基本になっているため、「重いフルコースの食事を、同じ雰囲気の中で連続して食べるのは、つらい経験になる」と感じているからだ。
では、連泊を増やしていくには何が必要か。星野氏はDXの観点で、星野リゾートで連泊を楽しめる仕組みを作る構想を明かした。
具体的には、星野リゾートの各宿泊施設の予約サイトで、連泊の宿泊予約をする時に、1泊目とは違った2泊目の食事アレンジを選び、予約できるようにすること。自社施設だけでなく、地域内の飲食店や体験事業者などからも選べるようにする。つまり、来訪者がタビマエで宿泊施設を軸にした地域での過ごし方をワンストップで予約できるサイトの構築だ。
例えば、星野リゾートの宿泊施設に3連泊する予定であれば、その予約のなかで、1泊目の夕食は館内で、2泊目の午前中は地域のアクティビティに参加し、夕食は地域の居酒屋で、3泊目は食事なし、という旅のプランが決められるというもの。ゆくゆくは、アクティビティや移動なども含め、タビナカ素材の予約もできるプラットフォームへの進化も視野に入れているという。
星野氏は「観光は地方において、今よりももっと重要な役割を果たせる。日本が観光立国を目指す理由も、地方経済への貢献を期待してのこと。私たちもそこを目指している」と、連泊推進に向けて宿泊施設が変革する意義を強調する。
 星野氏
星野氏
地域活性化は、国内旅行の成長が不可欠
日本が観光で成長していくためには、幾多の課題がある。そのなかで、星野氏が懸念していることの1つが、20代の旅行参加率の減少だ。
星野氏は、「日本全体の観光消費額は約20数兆円。その8割以上が国内在住者による需要であり、インバウンドが国の目標に達成しても、観光消費額の半分を超えることはない。最大セグメントの日本人の国内旅行を、次の世代のことも考えて策を打っていくことが一番大切」と訴える。
若者が旅行しやすい環境を作るには、何が必要か。まず1つが、割引などを含め、若者を旅行に促す施策の拡充だ。星野氏は陸上の交通では、新幹線網が整備されることで並走する在来線が減少するなどの問題をあげ、「以前のように安い値段でゆっくりと国内を回る旅行がしにくくなった。高額な新幹線はビジネス向けではあるが、若者のレジャーには向かない面もある。これが、観光消費額で交通費の割合が高い理由でもある」と指摘する。
また、星野氏が長く訴える「休日分散化」も不可欠。これに関して、星野氏は「驚きの動き」と歓迎しているのが、愛知県が2023年から開始した「愛知ウィーク」や「ラーケーション」だ。「愛知ウィークは11月だが、これに他の都道府県も追随すると、日本全国の休みが分散する。これこそ、中央政府ではなく地方からできる日本の変革の1つになると思う」と期待を込める。
新型コロナによるパンデミックで「生き残り計画」を社内外に公表し、需要消滅の時期を凌ぎながらも攻めの戦略も展開してきた。「大変だったが、組織全体で乗り切ることができ、経営者としては良い学びを得た」という星野氏。「観光産業全体としても、学ぶことが多かったのではないか」と話す。右肩上がりに伸びていた国内旅行市場だが、2019年はインバウンドを含め、綻びも見えていた。「あのまま進めば問題が噴出していたはず。それを、コロナを契機に見直すことができた」と自信を見せる。
国内外67軒に拡大した星野リゾートは、今後3年間でさらに10軒以上の開業を控える。コロナを機に、海外では「再生型観光」の文脈で、観光関係者だけでなく地域住民とともに観光振興に参加する動きが加速している。星野氏は、こうした取り組みを同グループの施設を拠点に、「ステークホルダーツーリズム」として推進しようとしている。
聞き手:トラベルボイス編集長 山岡薫
記事:山田紀子


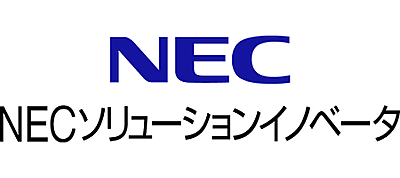















 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】