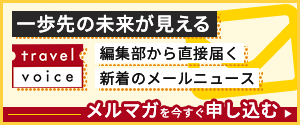コロナ禍は、観光が社会や経済に与える影響を、良くも悪くも浮き彫りにした。人の移動が制限され、各地の観光がリセットを余儀なくされたなか、コロナ以前は県内総生産(GDP)の2割を観光が占めていた“観光立県”の沖縄県は、どのように観光を再開していくのか。
国内・訪日・海外の本格的な旅行再開の期待に満ちた「ツーリズムEXPOジャパン(TEJ)2022」の会場で、沖縄観光コンベンションビューロー(OCVB)会長の下地芳郎氏に直撃して聞いてみた。
※編集部注:取材日は2022年9月22日の日中。同日夜に首相が入国規制緩和と全国旅行支援の開始の表明したため、追加取材を実施しています。
コロナが際立たせた観光の長所と課題
下地氏は、2年半超に及ぶコロナ禍によって、沖縄県では観光の持つ「重要性」と「脆弱さ」の2つの面が強調されたと話す。
1つ目の「重要性」については、「観光が沖縄経済にとって、大きな存在であることを再認識する機会になった」(下地氏)こと。観光は沖縄県の主要産業の1つであるが、それがどれくらいの影響があるものか、捉えきれていない県民も少なくなかった。しかし、観光客数がコロナの影響が全くなかった2018年度の約1000万人から2020年度は約250万人と4分の1程度になり、沖縄県のGDPが前年比9.8%減に落ち込むと、「さすがに観光が様々な産業に波及し、経済を支えていたことを実感した県民が多い」と、下地氏は話す。
もう1つの「脆弱さ」に関しては、観光の重要性とともに「観光は外的要因に弱い産業」という認識も広まった。下地氏によると、観光の危機時には官民が力をあわせて乗り切っていくのが「沖縄らしいやり方」。過去の9.11やSARSの時もそのように対応してきた。今回もいち早く観光と医療が連携し、2020年6月には空港内に「旅行者専用相談センター沖縄(TACO)」を設置。医療専門官と緊密に情報を取りあって、困難な状況に対峙してきた。
しかし、コロナは長期化し、断続的に感染の波が繰り返されたことで、「職業としての不安定さが印象づき、観光人材離れにつながっている」と下地氏。以前から観光の課題であった、労働環境の改善や生産性の向上の手が打てていない状況でコロナ禍に陥ったこともあり、既存の人材流出のみならず、観光分野への就職志望者の減少を危惧しているという。
ただし、コロナの影響は受けても「沖縄の観光の魅力が損なわれたわけではない」と下地氏。「これを乗り越えて、新しい観光の形をどう作っていくかが、問われている」と、コロナ明けの観光振興にむけて前を向く。
「責任ある観光」を現実的に推進するために
コロナによるリセットを機に、日本の観光地は「持続可能性」を重視した方針に舵を切っている。そのキーワードの1つに「量から質へ」「高付加価値化」が掲げられるが、下地氏は「量か質かの2択ではない。沖縄は両方とも大切」と話した。
目指すのは、「質を高めて、それに応じた量を増やす」こと。沖縄県では今後もホテル開業や本島北部でのテーマパーク計画など、観光投資が続いており、下地氏は「観光客の満足度を上げて観光消費の拡大と環境への配慮を促進し、それに応じる観光客を増やす。それが、沖縄の充実した観光インフラを活かすうえでも必要だと思う」と説明する。
 沖縄観光コンベンションビューロー(OCVB)会長の下地芳郎氏
沖縄観光コンベンションビューロー(OCVB)会長の下地芳郎氏
では、どのように進めていくのか。
下地氏は、「これは地域と観光客の思いが合致しないと実現しない。観光客に、島嶼県である沖縄の地域と環境を守る協力を促す流れをしっかり作っていく必要がある」としながらも、一方で「すべての人の旅行の意識がそこまで高いかというと、違うと思う」と、レスポンシブル・ツーリズム(責任ある観光)を推進する難しさも指摘。観光客にメッセージを発信しつつも、「改めて本格的なゾーニング(区域分け)の議論があってもいいのではないか」との考えを示した。
ゾーニングの方法として、エリアによっては人数制限や入域料徴収、ガイド同行の義務化などが考えられる。世界自然遺産に登録された本島北部のやんばる地域や西表島では、地域の観光協会が中心となり、こうした議論が徐々に始まっているという。
下地氏は、沖縄で観光の全体的な戦略として、沖縄全体のブランディングと同時に、各地域のブランド訴求を推進していることを説明した上で、「この両地域はそういうエリアであるという理解が深まっていけばいいと思う」との考えを示した。
そして下地氏は、那覇など吸収力がある都市部については一定数の人数が楽しんでもらえる場所としながらも、やはりそこでも「地元住民の生活に影響しないマナーが必要」と説明。「都市部のマナーと地域部のマナー、ルールはおのずと違う。それを無意識に守ってもらえるよう、取り組んでいきたい」と目指す姿を話した。
いよいよインバウンド本格再開、「地元が豊かさを実感できる形で」
今年の夏休み期間、沖縄県の国内旅行者数はコロナ以前の8割程度まで回復。全国旅行支援が始まればさらに増えるという自信を得た。
残る懸念は、インバウンド。
沖縄県は、コロナ以前(2018年度) の訪問者数約1000万人のうち約300万人は訪日外国人旅行者だった。だからこそ、入国者数制限の撤廃と訪日個人旅行の解禁、ビザ免除に、下地氏は「インバウンド本格再開に向けて大きな前進」と歓迎。チャイナエアラインが10月25日からの那覇線の再開を発表したことを踏まえ、他の航空会社にも積極的に働きかけていく考えだ。
しかし、諸手をあげて喜んでいるわけではない。インバウンドではまだ、国際クルーズの再開が認められていない。実は沖縄県の300万人の訪日観光客のうち、4割を占める120万人は海路からの入島。つまり、国際クルーズでの訪日客だ。下地氏は「国際クルーズによる観光振興と地域経済への貢献は大きい」との認識で、主要寄港地である石垣市と座間味町の首長とともに、国に対して国際クルーズの再開を要請してきた。
一方で、県内での国際クルーズに対する受け止めについて、「まだ県民の中でも、国際航空便と同程度には吹っ切れてはいないかもしれない」とも話す。しかし、「それは、多くの人がクルーズを知らないから。だからこそ私は、世界での運航再開の様子や、沖縄での寄港時における船会社の対策などを伝える国際クルーズのシンポジウムなどを開き、県民への理解促進をしていきたい」と意欲を示した。
同時に、国際クルーズの再開時には「ビジネスモデルを転換すべき」とも考える。「今までは単なる寄港地で、数時間滞在して出航。特に中国発着のクルーズは発地側ですべて仕込まれ、地域への還元が少なかった」と話し、今後はクルーズ前後の宿泊が期待できる航空便で沖縄を訪れ、沖縄の港から発着する「フライ&クルーズ」の振興も進めたい考えだ。
4年ぶりの東京開催となった今年のTEJ。沖縄からは各地から12団体が出展し、沖縄ブースに は4日間で合計4万5000人が来場した。出展団体数は、地元開催だった2019年(16団体)から減少したが、ほぼ遜色ない規模で揃い、下地氏も「沖縄の観光は各地のブランドを高めることが大切な時期に来ているなか、多くの市町村や事業者に参加していただけた。来場者も石垣や宮古など、個別の地域に対する質問も増えている」と、手ごたえを示す。
「地元が豊かさを実感できるかどうかが、最終的な価値判断になる」と下地氏。本格的に再スタートした沖縄の、新しい観光の形に注目したい。
 日本市場を主要ターゲットにした外国客船の国際クルーズの寄港も多い。撮影はコロナ前の2019年ゴールデンウィーク
日本市場を主要ターゲットにした外国客船の国際クルーズの寄港も多い。撮影はコロナ前の2019年ゴールデンウィーク


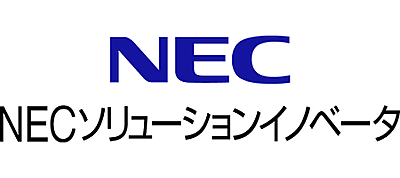















 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】