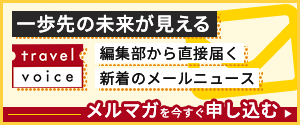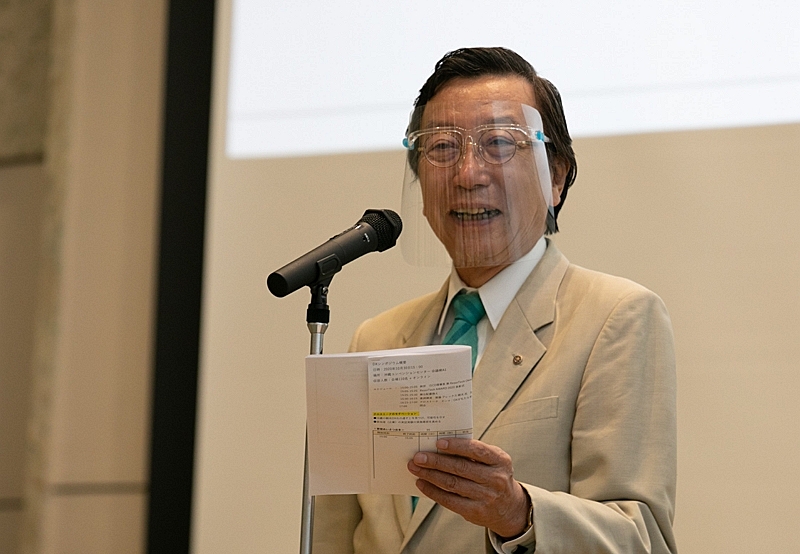
2020年10月に沖縄で開催されたツーリズムエキスポジャパン(TEJ)で、DX(デジタルトランスフォーメーション)をテーマにしたシンポジウムがおこなわれた。同シンポジウムを主催した沖縄ITイノベーション戦略センター(ISCO)の稲垣純一理事長は、「先端的なITを活用した国内外の事例から、ITや旅行に限らず、すべての産業界のみなさまに課題解決など気づきの機会としていただければと考えている」と挨拶した。
基調講演では、デジタルID活用先進国のエストニアからオンライン参加したxID社のビジネス開発部リード、齋藤アレックス剛太氏が、同国および日本国内での最新事例を紹介。続いてパネリスト4人を交えてのクロストーク・セッション「DXがもたらす沖縄観光の可能性とは」がおこなわれた。
エストニアや石川県加賀市の事例をヒントに
デジタルIDが登場して18年経つエストニアでは、現在、デジタルIDの普及率は99%に達しており、納税や自動車免許証など、行政サービスのオンライン化率も99%と高い。さらに銀行や学校はじめ、各種民間企業によるサービスでも日常的に利用されている。普及が世界に先駆けて早かった背景には「人口密度が非常に低く、国内各地に散らばって暮らしている国民に対して、限られた予算内で、効率的に公的サービスを提供する手法として、電子化が進んでいった」と齋藤氏は話した。
例えば、タリン市民向けの公共交通機関無償化の適用を受けるためには、利用者が自分の交通カード番号、ID番号、身分証のマイナンバーを入力するだけ。即時、その人がタリンに住んでいるかどうかを判定し、確認できれば即日、無料になる。電子納税申告システム(eTax)も、オンラインでの確認作業と電子署名で終了する場合が多く、便利でスピーディーなことが評価されており、エストニアでは税務申告の96%がすでに電子化されている。
エストニアのデジタルID制度では、電子取引のログをブロックチェーン上に保管する「KSIブロックチェーン」を活用することで、データの安全性を保持。またデータ管理においては、中央にすべてを集めて管理するのではなく、例えば「住民登録」「健康保障登録」「自動車登録」「銀行」など、データベースごとに管理するデータ連携基盤「x-Road」を構築。この仕組みにより、必要な人が必要に応じて必要なデータベースだけを、高速かつ安全に取り出すことができる。相互のデータベースのシームレスな連携も可能なので、デジタルIDで認証された利用については、各データベースに同じ情報を繰り返し入力する必要がない。
一方、スマートフォン人気に伴い、利用が急増しているのが携帯端末にインストールして使うアプリ版の「スマートID」で、ここ3年で国民への普及率は35%になった。ちなみにxID社が日本市場向けに開発しているサービスは、これと同様に、マイナンバーカードの機能を提供できるようにするデジタルIDアプリ。2020年夏から石川県加賀市で導入され、市が管轄する手続きはデジタル申請できるようになった。そのほか、茨城県つくば市ではマイナンバーを活用し、インターネット投票する実証実験が進行中だ。
 オンラインで出演した齋藤アレックス剛太氏(写真提供:ツーリズムEXPO推進室)
オンラインで出演した齋藤アレックス剛太氏(写真提供:ツーリズムEXPO推進室)
xIDが提供しているのは個人のエンドユーザー向けのアプリで、基本的な機能は「鍵(パスワード)」「ハンコ(電子署名)」「身分証明(政府が発行した公的なマイナンバーカード)」の3つの機能。これを様々な行政への申請や民間企業で使えるAPIにしたい考えで、メリットも多いと齋藤氏は話す。例えば本人確認や住所など、個人情報を繰り返し入力する必要がなくなるほか、パスワード不要になるので、同じものを使い回しているリスクを回避できる。
これを旅行業に活用する案として、齋藤氏は「宿泊者に何度も同じ情報を記入させる手間や、事業者側の確認の手間を省くために、宿泊施設の予約システムに電子IDを組み込むのはどうか。また沖縄のように、関係人口が多いところなら、自治体独自のe-Residency(電子住民)制度をつくり、訪問した人にマイルやポイントを付与する、電子市民だけを対象にした行政サービスを考案するなどが考えられる」と言及。
ただし、「デジタル化は目的ではなく、何かを解決するための手段」であると同氏は強調。「まずは課題を明確にすることから着手するべき。沖縄県のDXであれば、沖縄県のみなさんがどんなことを課題だと感じているのか。あるいは沖縄県を訪れる観光客にとって、どんなことが課題なのか。それを明確してからデジタル化に取り組むべき」と話した。
共通部品となるプラットフォームを積極活用
続くクロストーク・セッションでは、冒頭、モデレーターの稲垣氏が、DXの解釈について、「単なるデジタル化やIT活用ではなく、ビジネスモデルや組織を変革するもの、企業活動にとどまらず、社会や時代を形作っていく、それぐらいインパクトのある、人類史における根本的な次のステップだと感じている」と紹介。
続いて、なぜ今、日本においてDXが叫ばれているのかについて、シビックテックジャパン代表理事の福島健一郎氏は、人口減による人手不足の問題や、持続可能な社会作りが急務とあるなか「効率よく課題を解決する方法としてDXに注目が集まっていたところに、さらに新型コロナで拍車がかかった。なにしろデジタルは、人どうしの接触なしで物事を進められる、というのが根幹にある技術なので、コロナ対応に適している側面もある。ただ大事なのは、やはり課題解決に、どう技術を適用するのかだ。使うのは人間だというのも重要なポイントになる」と指摘した。
沖縄市で観光とスポーツ振興に取り組む同市経済文化部観光振興課主幹の宮里大八氏は、スポーツイベントなどでも「窓口での手続きが多く、その窓口も沢山ある。例えば体育館を使用したい場合、体育館の使用と、周辺の駐車場の利用は、それぞれ別の部署に申請する必要がある。予約も紙ベースで、毎月一回、特定の日に申し込むなど。こうした状況をDXで解決できれば、市民と競技者、両方へのサービス向上になる。コロナの影響もあるので、行政手続きをできるだけオンライン化し、サービスの付加価値を上げることが今の課題」と話した。
 シビックテックジャパン 福島氏(写真提供:ツーリズムEXPO推進室)
シビックテックジャパン 福島氏(写真提供:ツーリズムEXPO推進室)
 沖縄市経済文化部 宮里大八氏(写真提供:ツーリズムEXPO推進室)
沖縄市経済文化部 宮里大八氏(写真提供:ツーリズムEXPO推進室)
同シンポジウムでは、DX推進の問題点として、特に中小事業者や小さな組織にとってはハードルが高いことも指摘された。この点について、齋藤氏は「共通部品となるプラットフォームを利用するべきだ。加賀市でも、独自にプラットフォームを開発したわけではなく、ロゴフォーム電子申請というプラットフォームを利用した。すべて自前で開発すると、お金も期間も膨大にかかる。例えばオンライン会議のプラットフォームを、自治体や企業ごとに開発していたら大変だが、既存のZoomを活かせばよい。共通部品を積極活用するという視点は大事だ」。
福島氏は「我々も、各地にあるシビックテックの団体が手をつなぎ、共通の目的に取り組めるような方向に進んでいるところだ。色々な課題が出てくると思うが、同じ悩みを抱えている地域どうしが連携してプラットフォームを作る動きが、今後、活発になると思う。何もしないで待つだけという姿勢は一番よくない」とそれぞれ意見を話した。
また自治体におけるDX推進に対して「使い方が分からない」「一時的とはいえ、業務増える」など、ネガティブな反応が出た場合の対処方法について、宮里氏は「市町村、国など行政があまりに縦割りすぎたことが一因で、新しい業務へのチャレンジが難しく、前例やレガシーを受け継ぐことが優先されてきた。だが、いい意味でも悪い意味でも、コロナによって変わってきた。オンライン化できることはどんどんやるし、例えばこのシンポジウムのように、出張しなくてもオンラインで会えるようになった。今までとは違う価値観を生み出し、それが本当に市民のため、ビジネスのためになると理解してもらうことが大切だ」。組織内に評価する人がいなくても、周りに「これは絶対必要だから一緒にやろうよ」というステークホルダーをどんどん広げていくことが大事との考えを示した。
最後に、「沖縄でやりたい実証実験」に関する案を問われると、福島氏は「シビックテックの観点からは、行政が持っているたくさんの観光資源、情報データをオープンに利用できるような仕組みを構築することが大事なので、そのお手伝いならできると思う。例えば沖縄の写真。著作権に問題ないものを公開して出していただきたい。さらに民間企業や市民個人の力を借りて、お店情報や観光情報も加えた新しい観光情報サービスができるのではないか」と提案。
宮里氏は「個人のアイデア」と断った上で、2年前、琉球大学に勤務時代、台湾と香港を訪れた時の経験から、「沖縄版のデジタル通貨ができないかと考えている。沖縄に来た外国人観光客が、スマホだけでデジタル通貨の決済を完結できる仕組み。コロナの影響で人の移動が難しくなっているが、来年、再来年に向けて、沖縄のどこでも使えるデジタル通貨の仕組みがあったらいい。認証もできるので、安心安全な観光にもつながる」とのアイデアを披露した。


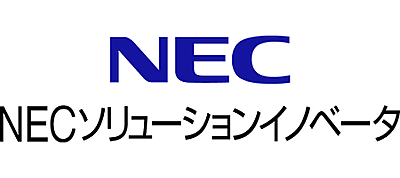















 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】