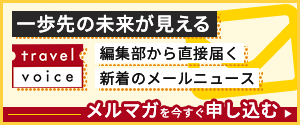コロナ禍で主戦場の海外現地ツアーの販売が不可能になり、一時は売り上げの99.8%が消滅したベルトラ社。事業継続を模索し、オンラインツアーや国内現地ツアーに本格参戦するなか、「いくつか大きな気づきがあった」と、代表取締役社長兼CEOの二木渉氏は話す。
旅行会社でありながら、今春、再定義したコーポレートミッションから「旅」という文言を外し、社員には「旅行会社になってはならない」と話した。「移動ができない世界なんて、想像すらできなかったことが現実に起きた。旅は移動が前提という考えは、やめなくてはいけない」という二木氏に、その真意と今後の戦略、日本のタビナカ市場の課題を聞いた。
移動ができない世界に直面して生まれた革新
ベルトラが2022年3月末に発表した新コーポレートミッションは、「心ゆさぶる体験を未来に届ける」。刷新を決めたのは、コロナ前の2019年末だった。その当時、用意した文言は「心ゆさぶる旅の体験を未来に届ける」だったが、発表時には「旅」の文字を外した。「旅での体験に限ると、心ゆさぶる体験の領域は狭まる。我々が目指すのは移動ありきのものではない」(二木氏)というのが理由だ。
同社が定義する「心ゆさぶる体験」とは、「世界中の文化や自然、それを伝える人々の素晴らしさを、心の底から実感できる本物の体験」(二木氏)。以前から同社に根付く考えだが、旅ではなく、心ゆさぶる体験こそがサービスの核であると認識したきっかけは、コロナ禍の2020年7月に開始したオンラインツアーだったという。
コロナ禍で新たな収入となる期待もあって始めたものだったが、そのうちに「現地に直接行かなくても、参加者が満足できる価値を提供できる」(二木氏)と確信した。「文化・教養系の講座はコロナ以前からオンライン化が進んでいたが、旅行も学びの体験」(二木氏)であるからだ。
そこで、二木氏は同社の事業ポートフォリオを「心ゆさぶる体験に出会うためのソリューションを提供すること」と定義。「そうなると、旅行業であることは重要でなくなる。むしろ、旅行業の枠を超えた発想で、商品やソリューションを作っていく必要がある」という考えに至った。
今でこそ、タビナカは多くの競合がひしめく市場になったが、ベルトラがこの事業を開始した2004年当時は、旅先の現地ツアーや体験のみを扱う専業の事業者は他にいなかった。だからこそ、「旅行業とは違う分野で市場を作り、規定概念にとらわれないアプローチができていた。もともと当社は、旅行業ではないという前提で成り立っている」(二木氏)という自負が強い。
企業ビジョン・ミッションの刷新の際、社員に発した『旅行会社になるな』のメッセージには、「旅行業の常識だけで考えてはならない」という自社のカルチャーの原点回帰や強みの再認識を促す思いが含まれているという。
 ベルトラ代表取締役社長兼CEOの二木渉氏
ベルトラ代表取締役社長兼CEOの二木渉氏
国内商品の開始で直面した課題、「食」の可能性
すでに同社は新たな挑戦を始めている。その1つが、国内タビナカ市場への参戦だ。コロナ前はコア事業の海外に加え、インバウンドにも取り組み始めていたところだったが、2020年からは日本人をターゲットにした本格的な国内体験ツアーの取り組みを開始した。
二木氏は、「海外商品だけでは顧客接点が少ないので、当社会員とのライフタイムバリューを高めるために、利用頻度が高い国内で体験を提供したいと思っていた」としたうえで、「海外事業ではパリ発のモンサンミッシェルツアーのように、現地事業者と商品開発をし、市場を開拓してきた例が多くある。この経験を、日本でも役立てることができる」と、国内参戦への本気度と自信を示す。
すでに長崎港発着の「五島列島日帰りツアー」など、「長崎市内からちょっと足を伸ばしてみようと思えるアプローチ」(二木氏)で、旅先のその先へ送客する商品も販売。また、今年4月には環境省と「国立公園オフィシャルパートナーシップ」を締結し、国立公園でのエコツーリズムやアドベンチャーツーリズムなどの商品拡充や、ピースツーリズムを推進することも決まっている。
こうした取り組みの中で、海外のタビナカをよく知る二木氏は、「日本のタビナカの産業構造を変える必要がある」という、課題感を持つようになったという。
その課題とは、タビナカ事業者の持続可能性。まずは商品の価格と内容を比較すると、一般的な国内ツアーアクティビティの価格は、ほとんどが1万円以下。海外では1万円以下の商品は全体の3割程度で、7割以上が1万円以上だ。商品内容を見ると、海外では食事が含まれているものが全体の8割であるのに対し、日本では3割程度にとどまる。そして送迎は、日本の場合は法制度の問題で踏み込むことができない事業者が多い。
「結果として、日本はタビナカ商品全体の単価と収益性が乏しい。アクティビティ単体での収益だけで事業を成り立たせなくてはならず、ジリ貧になってしまう。そこに送客しようと、販売業者がプロモーションを展開しても、収益性は何も解決しない」(二木氏)と、問題点を指摘する。
商品内容による販売額の差を見ると、「参加者が送迎の要否を選べる商品」は「送迎がない商品」の3.8倍。「食事付の商品」は、「食事のない商品」の5倍の販売額になるという。二木氏は、「このアプローチが国内で全然できていない。これは日本にとって本当にもったいない」と話す。
特に食事に関しては、「日本のように、それぞれの地方の飲食を地域の文化として打ち出せる国は、世界でも数少ない。それなのに、アクティビティ参加者は弁当をコンビニで購入している」と指摘。「日本が魅力的な現地体験を提供するためにも、飲食をその土地の文化や風土を体験するものとして捉え、アプローチすることが商機につながる。旅行における日常消費を排除することが、付加価値になる」と力を込める。
 ベルトラ二木氏
ベルトラ二木氏
二木氏は海外の観光事業者の姿について、「海外では小規模の観光事業でも成功している経営者も多く、生活にゆとりがあると思う」と話す。これ対して日本のタビナカ事業者は収益性が相対的に低く、一部地域では季節性で限られたシーズンにしかサービスを提供できないこともあり、副業などをしながら持続する事業者も多いというのが一般的な見方だろう。
「日本では、その地域やその体験が好きだから、その魅力を伝えたいとの思いで事業をしている方が多い。ただし、事業の継続性は、そこで働く人々が仕事に魅力を感じ、生活ができる基盤があることが前提。我々は、そういうバランスの部分を海外で目の当たりにしてきた。その知見を活かし、国内のポテンシャルを最大限引き出せる方法があると思っている」(二木氏)。
ベルトラの2大事業
二木氏によると、国内にも本腰を入れるとはいえ、事業のコアは「あくまでも海外」。ただし、国内も「海外と同等くらいまで行けると思う」と自信をのぞかせる。
一方、ベルトラでは傘下にBtoBのEチケットプラットフォーム「リンクティビティ」を持つ。日本でのインバウンドが拡大する中、訪日外国人が国内のアクティビティにアクセスしようにも、そこに到着するための交通に不便を感じていた。その解決を図ろうとしたのが、同事業の起点だ。
コロナ禍の2020年3月の船出となり、まだ本領を発揮できていないが、この2年間、着実に国内の提携先を広げてきた。二木氏は、「これは、インバウンド3000万人による国内交通5000億円市場、そして国の目標である6000万人時代の国内交通1兆円市場に対するソリューション事業。コロナが収束し、訪日客が戻るのが楽しみなところ」と、笑みを見せる。
ベルトラはBtoCのOTA事業、リンクティビティはBtoBの観光IT事業と異なるが、「すべては『心ゆさがる体験』を届けることでつながっている」と二木氏。OTA事業で心ゆさぶる体験を作り出し、観光IT事業でそこに行き着くソリューションを提供する。目指す体験価値の提供へ、新たな舵を切っている。
 ロゴデザインも刷新。ワクワクするようなシームレスな体験、人の存在を感じられる親しみやすさを表現したという
ロゴデザインも刷新。ワクワクするようなシームレスな体験、人の存在を感じられる親しみやすさを表現したという


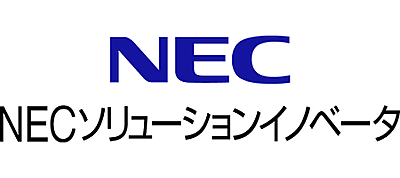















 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】